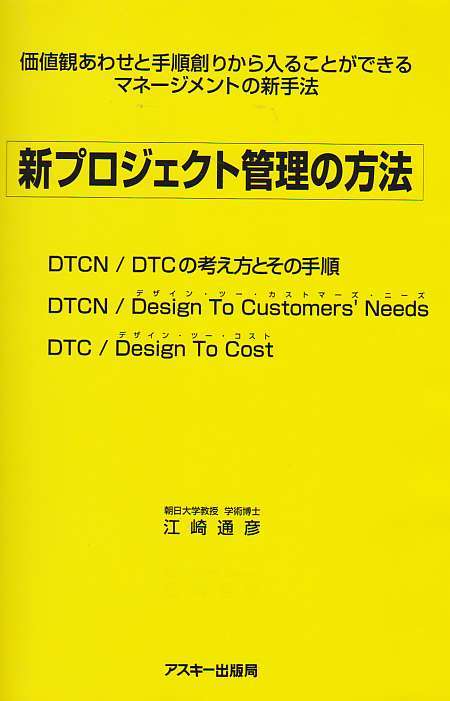 丒怴偟偄僥乕儅
丒怴偟偄僥乕儅丂奐敪偑姰椆偟丄俿亅係偺検嶻懱惂偑屌傑偭偨帪揰偱丄拞摍楙廗婡愝寁幒偼夝懱偝傟丄僾儘僕僃僋僩傪揨傔傞峲嬻婡愝寁晹偲婡擻扴摉晹偵暘偐傟偰恖堳偼堎摦偡傞偙偲偵側傝丄1989擭7寧丄巹偼峲嬻婡愝寁晹乮娾寧晹挿乯丒僔僗僥儉娗棟壽偵攝懏姺偊偵側偭偨丅偲偼偄偭偰傕摉弶偺巇帠偼憡曄傢傜偢俿亅係偺怣棅惈丒惍旛惈偺岦忋偱偁偭偨偑丄偟偐偟偙偺帪婜丄婔偮偐偺怴偟偄僥乕儅傕晅偗壛傢偭偨丅挌搙庡嵏乮壽挿懸嬾乯偵徃恑偡傞僞僀儈儞僌偱丄1990擭4寧偑偦傟偱偁偭偨丅
丂偦偺傂偲偮偑娵慞偐傜弌斉偝傟偰偄傞峲嬻岺妛曋棗偺夵掶斉嶌惉偱偁傞丅怴偟偄僾儘僕僃僋僩偑弌棃忋偑傞偲摨帪偵丄偦偺嬈愌傪僴儞僪僽僢僋偲偟偰屻悽偵巆偡偺偱偁傞偑丄偦偺拞偵偄偔偮偐巹偑娭梌偟偨僥乕儅傪嵹偣傞傛偆偵偄傢傟偨偺偱偁傞丅尷傜傟偨僗儁乕僗偵偆傑偔梫栺偡傞偙偲偑媮傔傜傟丄擄偟偐偭偨偑椙偄宱尡偵側偭偨丅偪傚偭偲梋択偵側傞偑丒丒丒偙偺帪偍悽榖偵側偭偨偺偑屻偵挬擔戝妛戝妛堾嫵庼偵側傜傟偨峕嶈捠旻偝傫偱丄偙傟埲慜偵傕峕嶈偝傫偵偼僾儘僕僃僋僩娗棟庤朄偱偄傠偄傠嫵偊偰偄偨偩偄偰偄偨丅摿偵乻壗偺偨傔偵乼傪忋埵偵丄乻偳偺傛偆偵乼傪壓埵偵偟偰亀栚揑亅庤抜亁偺娭學傪柧帵偡傞庤朄偼屄恖揑偵傕椙偔巊傢偣偰傕傜偭偨丅傑偨丄俙俼俿俤俵俬俽偲偄偆柤偺僾儘僕僃僋僩娗棟僜僼僩傪俲俙倂俙俽俙俲俬偑惗嶻岺掱娗棟偵摫擖偡傞嵺偵僉乕儅儞偲側偭偨曽偱傕偁傝丄僪僋僞乕僿儕偺崙撪摫擖偵傕峕嶈捠旻偝傫偼僂僨傪怳傞偭偰偄傞丅乻幨恀偼峕嶈偝傫偺挊彂乼丂偝偰丄僴僫僔傪栠偦偆丅
丂
丂擇偮栚偑亀恖岺抦擻亁偺峲嬻婡惍旛傊偺揔梡尋媶偱偁傞丅拞摍楙廗婡愝寁幒帪戙偺嵟屻偺偁偨傝丄摉帪偺屻曽巟墖扴摉壽挿偩偭偨嫶杮庡嵏偺娞偄傝偱丄幮撪尋媶旓梡傪巊偭偰丄杮幮媄弍奐敪杮晹偺媨杮偝傫偑悇恑偟偰偄偨俲俬俽乮Kawasaki丂Inference丂System乯傪儀乕僗偵俿亅係婡偺屘忈扵媮僔僗僥儉偺儈僯儌僨儖傪嶌傝丄偄傠偄傠側偲偙傠偵攧傝崬傒傪偐偗傞傋偔丄摉帪巹偺晹壓偵側偭偨偽偐傝偺KHI/KGE偺怴擖幮堳丒垻晹丒嶳揷丒悮壀丒姛愳孨偨偪偲僠乕儉傪慻傫偱怴偟偄媄弍傊偺傾僾儘乕僠傪巒傔偰偄偨丅偪傚偆偳帪戙偑俠俙俴俽僉儍儖僗乮Computere Aided Logistic Support乯偵嵎偟妡偐偭偰偄偨偺偱偁傞丅寢壥偲偟偰丄偙偺恖岺抦擻偺尋媶偼丄奀忋帺塹戉偺尋媶旓梡傪偄偨偩偄偰俽俫亅俇侽俰僿儕僐僾僞乕偺惍旛巟墖傪懳徾偲偟偨億乕僞僽儖丒僷僜僐儞乮搶幣幮偺儔僢僾僩僢僾僷僜僐儞傪巊偭偨偺偩偑丒丒丒乯偱偺帋嶌傑偱恑傒丄屻擔丄乻俙倂俙俠俽惍旛庢愢偺婡夿東栿乼偲偄偆宍偱幚傪寢傇偙偲偵側傞偺偩偑丒丒丒偦偆偙偆偟偰偄傞偆偪偵峲嬻俀壽乮峲嬻帺塹戉偺屌掕梼僾儘僕僃僋僩扴摉丟惣榚壽挿乯偺堦晹偵側偭偨偺偑92擭偺7寧丄嵞搙僔僗僥儉娗棟壽挿偵側偭偨偺偑93擭7寧偲偄偆偙偲偱丄枅擭柤巋偺尐彂偒偑擖傟懼傢偭偰偄偨丅
丂嶰偮栚偼丄側傫偲俥俽倃丗俲俫俬攈尛僠乕儉偺僒億乕僩偩偭偨丅偙傟傛傝彮偟慜丄1985擭崰偐傜杊塹挕偼巟墖愴摤婡俥俽偺奐敪傪峴偍偆偲偟偰偄偨丅摉弶偼崙嶻奐敪楬慄偱偁傝丄偙偺弨旛傕寭偹偰俿亅係傕偝傑偞傑側僔僗僥儉娗棟妶摦傪乮梊峴墘廗偺宍偱乯峴偭偰偄偨偺偩偑丄亀暷崙偺朩奞亁偱娞怱偺僄儞僕儞媄弍偑弌偟偰傕傜偊側偄丅偦偙偱傗傓側偔俥亅侾俇傪夵憿奐敪偡傞偙偲偵側偭偨丒丒丒偲暦偄偰偄傞丅奐敪偺庡懱偼俵俫俬偲僕僃僱儔儖丒僟僀僫儈僢僋僗偱偁傞偑丄擔杮懁偼偄偮傕偺傛偆偵僆乕儖僕儍僷儞偲偄偆偙偲偱丄倃俿亅係偱揹憰斍傪棪偄偨嶁杮孨偑俲俫俬戙昞偱攈尛偝傟偨丅俲俫俬懁偺媄弍憢岥乮偲偄偭偰傕幚偼乽媄弍幰偺攈尛帠柋乿偑庡偩偭偨偑乧乯偼巹偑扴摉偟偨丅1990擭偺偙偲偱偁傞丅
丂僾儘僕僃僋僩娗棟偱嵟弶偵栤戣偵側傞傕偺偺傂偲偮偼梊嶼攝暘偱丄憗懍巹偼嬈柋偺昹揷壽挿偲嫟偵俵俫俬傊宊栺僱僑僔僄乕僔儑儞偵弌妡偗偨丅偦偙偱憢岥偲偟偰弌偰偒偨偍曽偑丄側傫偲丄倃俿亅係偱墢偺偁偭偨偁偺亀墦摗偝傫亁偩偭偨丅亀偙偺慜偼偁側偨偺尵偄暘傪暦偄偨偺偩偐傜丄偙傫偳偼巹偺尵偄暘傪暦偄偰偔偩偝偄亁偲偄偆挷巕偱丄側傫偲偐僗儉乕僘偵偙偲偑塣偽偣偰栣偭偨偺偼戝曄儔僢僉乕偩偭偨偲巚偆丅強慒丄奐敪偼僸僩偑峴偆偺偱偁傞丅丂偙偺俥俽倃偱俲俫俬偼乽拞晹摲懱乿乽僄儞僕儞偺傾僋僙僗僪傾乿傪暘扴惗嶻偡傞偙偲偵側傞偑丄拞晹摲懱偵廂擺偝傟傞乻庡媟乼偺扴摉偱傕傔丄偡偭偨傕傫偩偺憶偓偑偁偭偨傕偺偺丄側傫偲偐嬈柋偺昹揷壽挿偲巹偲偱婃挘傝丄俵俫俬偲偺棟榑摤憟偵懪偪彑偮偙偲偑偱偒偨丅偙偺審偱偼摉帪偺戝撪揷帠嬈晹挿傪彮乆嬃偐偣偨敜偱偁傞丅
丂丒丒丒偦偺俀擭屻丄巹偼俵俫俬偺彫杚岺応偱倃俥亅俀偺儌僢僋傾僢僾偵嵹偣偰傕傜偭偨丅憖廲惾偵忔傝崬傓偲丄偆傢偝偳偍傝亀偐側傝忋岦偒亁偵嵗傞丅偦偟偰摿挜揑側僒僀僪僗僥傿僢僋偑僾儗僢僔儍乕傪壛偊傞偲丄偦傟偵墳偠偰彮偟偩偗曄埵偡傞偙偲傪妋擣偟偰婌傫偱偄偨偙偲傪丄崱巚偄婲偙偡偺偱偁傞丅
